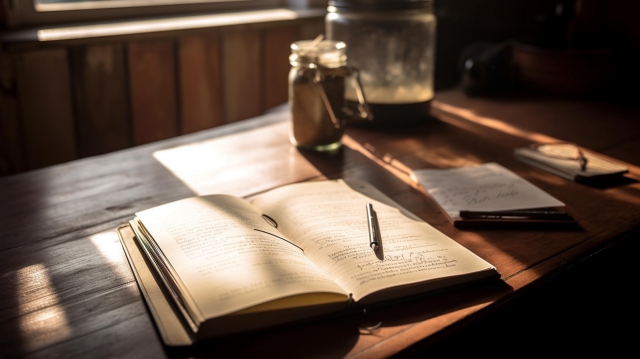■技術士には書く能力が求められている
技術士に求められる7つの資質能力(コンピテンシー)の一つである「コミュニケーション」は以下のように定義されています。
–
業務履行上,口頭や文書等の方法を通じて,雇用者,上司や同僚,クライアントやユーザー等多様な関係者との間で,明確かつ効果的な意思疎通を行うこと。
=
–
このように,技術士には,文書を通じた明確かつ効果的な意思疎通を行う能力が求められています。つまり,技術士には書く能力(=書く力)が必要だということです。
–
例えば,「在宅勤務の問題を1つ述べよ」という問題に対して以下のような内容(解答)では,解答を通じた試験官との明確かつ効果的な意思疎通ができません。
–
【パターンⅠ】
会社内で仕事を行う場合には,社内のセキュリティによって会社内にある情報が外部に流出する危険性は小さい。しかし,在宅勤務になると,自宅で使うパソコンのセキュリティが会社のセキュリティに比べて脆弱になる。そのため,在宅勤務によって情報が外部に流出する危険性が出てくる。
以下のように書くことで,解答を通じた試験官との明確かつ効果的な意思疎通ができます。
【パターンⅡ】
在宅勤務の問題は,情報漏洩の危険性が出てくることである。会社内で仕事を行う場合には,社内のセキュリティによって会社内にある情報が外部に流出する危険性は小さい。しかし,在宅勤務になると,自宅で使うパソコンのセキュリティが会社のセキュリティに比べて脆弱になる。そのため,在宅勤務によって情報が外部に流出する危険性が出てくる。
■筆記試験(記述式試験)では書く力が求められる
記述式試験では書く力が求められています。書く力に関することがコミュニケーション(コンピテンシー)の定義に書いてあるからです。すなわち,受験生には,試験官と明確かつ効果的な意思疎通ができる論文(答案)(=解答が明確に伝わる〈論文・答案〉)を書く力が必要です。例えば,「パターンⅡ」ように解答が明確に伝わる論文(答案)を書く力のことです。
合格点に達している解答を書くことが合格のための最も重要な条件です。しかし,試験官と明確かつ効果的な意思疎通ができる論文(解答)を書くことも合格の条件です。技術士には,書く力が求められているからです。
次回に続きます。