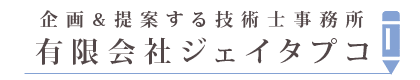「内容が明確に伝わる技術文書の書き方」の考え方を使った技術士二次試験対策です。具体的には,「書き方1:要点を冒頭に書く」を使った「1分で理解できる解答」を書く方法の解説です。
「解答として何を書くのか」ではなく「頭の中にある解答をどのように書くのか」に重点を置いた内容です。
1.1 「1分で理解できる解答」とは
以下のような問題があったとします。
【問題】
在宅勤務の問題を1つ述べよ。
ここで,以下のような解答を書いたとします。
このような解答を読むと「内容はわかる。でも,結局,何が言いたいのだろう」と思いこの解答の要点(解答の主旨)を読み取る必要があります。このような解答を書くと内容が1分では理解できません。
次に,以下のような解答を書いたとします。
解答の要点(解答の主旨)として,「在宅勤務の問題とは,情報漏洩の危険性が出てくることである」を書きその後にこれに関する説明を書いています。このように,解答の要点とこれに関する説明が書いてある解答を読むと内容が1分で理解できます。これが,「1分で理解できる解答」です。
ー
1.2 小問に対して書く
小問に対して,「“1分で理解できる解答”の書き方」に基づき解答を書きます。小問とは,必須科目および選択科目で出題される問題です。
Ⅰ.必須科目:(1)~(4)の小問が出題されます。
Ⅱ.選択科目
=①専門知識:専門知識では,「述べよ」と「説明せよ」など1つの問題の中で複数の問題が出題されます。すなわち,専門知識の問題は複数の小問に分かれています。
=②応用能力:(1)~(3)の小問が出題されます。
=③問題解決能力及び課題遂行能力:(1)~(3)の小問が出題されます。
_
2.1「書き方1:要点を冒頭に書く」を使う
「書き方1:要点を冒頭に書く」を使って「1分で理解できる解答」を書きます。ここで,「書き方1:要点を冒頭に書く」とは,「6つのルールと18の書き方」注1)の中での書き方の一つです。また,書き方1とは,「内容に関する要点を冒頭に書き,この要点に関する説明をその後に書くこと」です。
【6つのルールと18の書き方】
| ルール | 書き方と内容 | ||
| ルール1 | 冒頭に書く | 書き方1 | 要点を冒頭に書く |
| 書き方2 | 全体像を冒頭に書く | ||
| 書き方3 | 枠組みを冒頭に書く | ||
| ルール2 | ペアで書く | 書き方4 | 根拠を書く |
| 書き方5 | 条件を書く | ||
| ルール3 | 分けて書く | 書き方6 | かたまりに分けて書く |
| 書き方7 | 箇条書きで書く | ||
| 書き方8 | 表で書く | ||
| ルール4 | 視覚的に書く | 書き方9 | 写真や図を入れて書く |
| 書き方10 | 強調して書く | ||
| 書き方11 | まとまりを持たせて書く | ||
| ルール5 | 合わせて書く | 書き方12 | 組み合わせて書く |
| ルール6 | 明確に伝わる文を書く | 書き方13 | 具体的な文を書く |
| 書き方14 | 意味が明確な文を書く | ||
| 書き方15 | 能動態の文を書く | ||
| 書き方16 | 短い文を書く | ||
| 書き方17 | 肯定文で書く | ||
| 書き方18 | 文法を守って文を書く | ||
=注1):「6つのルールと18の書き方」とは,「内容が明確に伝わる技術文書の書き方の技術」の一つです。
ここで,技術士二次試験では,「内容に関する要点(内容の要点)=解答の要点」,「内容の要点に関する説明(要点の説明)=解答の要点に関する説明(要点の説明)」とします。
ー
2.2 解答の要点と要点の説明を考える
(1)解答の要点と要点の説明とは
「1分で理解できる解答」を書くうえでのポイントは,解答の要点と要点の説明を考えることです。
①解答の要点とは,試験問題の中で示された「解答すること注2)」に対する要点です。また,解答の要点とは,「解答を簡潔に言ったこと」あるいは「解答を一言で言ったこと」と言い換えることができます。
=注2):例えば,以下のような問題での「解答すること」とは,課題,観点および課題の内容(アンダーラインの箇所)です。
「建設分野におけるCO2排出量削減及びCO2吸収量増加のための取組を実施するに当たり,技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,課題の内容を示せ。」
②要点の説明とは,「解答の要点を説明する内容」あるいは「解答の要点に関する内容」です。
(2)解答の要点と要点の説明の具体的な内容
「1.1 『1分で理解できる解答』とは」で解説した問題とその解答を使って,解答の要点と要点の説明の具体的な内容を解説します。
=①「解答すること」とは,「在宅勤務の問題」です。
=②解答の要点(=解答を簡潔に言ったこと,解答を一言で言ったこと)とは,「情報漏洩の危険性が出てくること」です。
=③要点の説明とは,以下の内容です。つまり,「情報漏洩の危険性が出てくること」を説明する内容あるいは「情報漏洩の危険性が出てくること」に関する内容です。
解答の要点と要点の説明を書くことで解答が1分で理解できます。
=
2.3 解答の要点と要点の説明に基づき解答を書く
(1)基本の書き方
解答の要点と要点の説明に基づき解答を書きます。このとき,以下のように,解答の要点を解答の冒頭に書き,この要点の説明をその後に書くことが,「1分で理解できる解答」を書くうえでの基本の書き方です。
ここで,橙色で着目した内容が解答の要点です。緑色で着目した内容が要点の説明です。
(2)解答を複数書く場合
令和4年度の試験では,総合技術監理部門を除くほとんどの部門の必須科目で以下のように課題を複数書く問題が出題されました。
「・・・多面的な観点から3つ課題を抽出し・・・」
解答を複数書く問題では以下のように書きます。
(1)維持修繕に係わる技術者の不足
現行の基準では,橋梁や道路トンネルの点検は,近視目視や打音検査などで行うことになっている。この点検では技術者が直接検査を行うため経験に基づく技術力やノウハウが要求される。また,診断結果に基づく措置に対しても同様の技術力が要求される。
・・・以下,略・・・
(2)維持修繕工事の不調・不落
維持修繕工事は,建設会社にとって魅力のない業務である。現状での維持修繕工事の不調や不落の発生がこれを証明している。この理由として「積算金額と実勢価格がかい離している」,「小規模,複雑な案件が多く効率的に業務を行うのが困難」などがある。
・・・以下,略・・・
ここで,橙色で着目した内容が解答の要点です。緑色で着目した内容が要点の説明です。すなわち,この書き方は,解答の要点を見出しとして書き,この見出しの説明(要点の説明)をその後に書く書き方です。このような書き方も,「解答の要点を解答の冒頭に書き,この要点の説明をその後に書く書き方」です注3)。
=注3):このような書き方は,「6つのルールと18の書き方」の中での「ルール3・書き方6:かたまりに分けて書く」の考え方に基づく書き方です。
(3)注意点
「1分で理解できる解答」を書いても,解答の要点と要点の説明が合格点以下の内容では不合格になります。合格点が取れる解答の要点と要点の説明を書いてください(考えてください)。
ー
2.4 解答の要点を書くときのポイント
(1)基本の書き方
解答の要点を書くときのポイントとは,「解答すること」を主語とした文を書くことです。「解答すること」を主語とした文を書くと「解答すること」と「解答の要点」の関係が明確になります。
=◆解答すること⇒在宅勤務の問題
=◆解答の要点⇒在宅勤務の問題は,情報漏洩の危険性が出てくることである。
このような書き方が,「1分で理解できる解答」を書くときの基本の書き方です。
令和5年度の建設部門の必須科目では以下のような問題が出題されました。
(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。
この問題での「解答すること」とはリスクと対策です。すなわち,「解答すること」を主語とした文を書くとは,「リスク・・・・である」や「対策は・・・である」のように書くことです。
(2)基本以外の書き方
試験では,概要,原理,実用例,手順など様々な「解答すること」が出題されます。これらのような単語を主語とした文(概要とは,・・・)が書きにくい場合には,別の主語を使って文を書いても構いません。このような単語は専門知識の問題で多く使われています。
ここで,「概要」の解答を書く場合を以下に示します。
*「横ボーリング工の概要を述べよ」という問題の場合
_◆横ボーリング工とは,地盤内の地下水を排出し地下水位を低下させる工法である。降雨による地下水の上昇が地すべりの原因である。そこで,地下水位を低下させ,すべり面に働く間隙水圧を低減させたり,地すべり土塊の含水比を低下させたりする。
*アンダーラインの箇所が“概要の要点”です。
また,「2.3,(2)解答を複数書く場合」で示した例も基本以外の書き方です。「解答すること」を主語として解答の要点を書いていません。つまり,「課題は・・・である」のような書き方をしていません。
「解答すること」に対応して解答の要点を書く方法を考えてください。
ー
解答の要点と要点の説明が書いてあるので試験官に解答が明確に伝わるからです。つまり,問題に対する自分の考えとそれを説明する内容が明確に書いてあるからです。また,解答の要点と要点の説明が書いてあるので,何度も読み返さずに一度読んだだけで解答が理解できるからです。「結局,何が言いたいのだろう」と考える必要がありません。
ー
試験場では,以下の手順で「1分で理解できる解答」を書いてください。
①問題を読み「解答すること」を確認する。
*「解答すること」にアンダーラインを引くと確実に確認できます。
②「解答すること」に対する解答の要点を考える。
③要点の説明を考える。
④解答の要点と要点の説明を使って解答を書く。
ー
森谷仁著,「マンガでわかる技術文書の書き方」,オーム社,令和4年3月25日
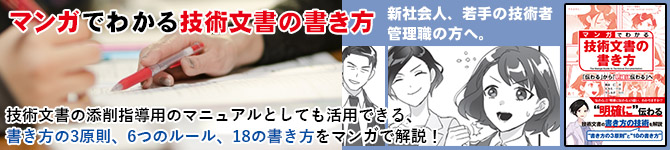
*「内容の要点を簡潔に書くこと」など「書き方1:要点を冒頭に書く」に関して詳しく解説しています。書き方1の他,文の書き方として,文を簡潔に書く書き方(文を短く書く書き方)なども解説しています。
_
6.1 トレーニングの必要性
「1分で理解できる解答の書き方」に基づき解答を書くためのトレーニングが受験勉強の中でできます。このトレーニングをしておくと問題を読んだら,すぐに,「解答の要点と要点の説明を考えよう」のように頭を切り替えることができます。
ー
6.2 トレーニングの方法
過去問を使ってトレーニングをします。過去問を読み,解答の要点と要点の説明をノートなどに書き出します。このとき,解答の要点と要点の説明のポイントがわかる程度の書き出しで構いません。「解答の要点と要点の説明を考えよう」のように頭を切り替えるためのトレーニングだからです。
「スマートインターチェンジの特徴を述べよ」という問題があったとします。この問題に対して例えば以下のように書き出します。
=■解答の要点
==従来のインターチェンジに比べてその設置や維持管理のコストの削減が可能
=■要点の説明
==「簡易な料金所,料金徴収員不要,維持管理費削減」などについて書く
ここでは,解答の要点の書き出しは文で,要点の説明の書き出しは要点の説明に書く内容のキーワードを書き出しました。書き出しの方法に決まりはないので自分がわかやすい内容で書き出してください。
ー
6.3 受験勉強になる(自分の弱点がわかる)
このトレーニングは,過去問を使った受験勉強にもなります。「解答の要点と要点の説明が書き出せなかった場合にはその過去問を解くことができない」ということです。すなわち,この過去問の内容に関する技術や知識が弱点(勉強不足)だということです。令和元年度から令和4年度までの問題に対してこの練習をして自分の弱点を見つけてください。自分の弱点がわかれば勉強すべき内容も明確になります。
=
【参考ブログ】
■技術士二次試験対策:「解答を考え・解答を書くこと」を単純化する
■技術士二次試験対策:「“1分で理解できる解答”の書き方」のトレーニング方法
■技術士二次試験対策:会話でトレーニングする方法
■技術士二次試験対策:解答の要点を考えることが重要
■技術士二次試験対策:「要点の説明=解答の要点を支えるもの」
■技術士二次試験対策:インプットの受験勉強とアウトプットの受験勉強(その1)
■技術士二次試験対策:インプットの受験勉強とアウトプットの受験勉強(その2)
■技術士二次試験対策:解答の要点を簡潔に考える(その1)
■技術士二次試験対策:解答の要点を簡潔に考える(その2)
■技術士二次試験対策:技術士二次試験は記述式試験
■技術士二次試験対策:脳のトレーニング