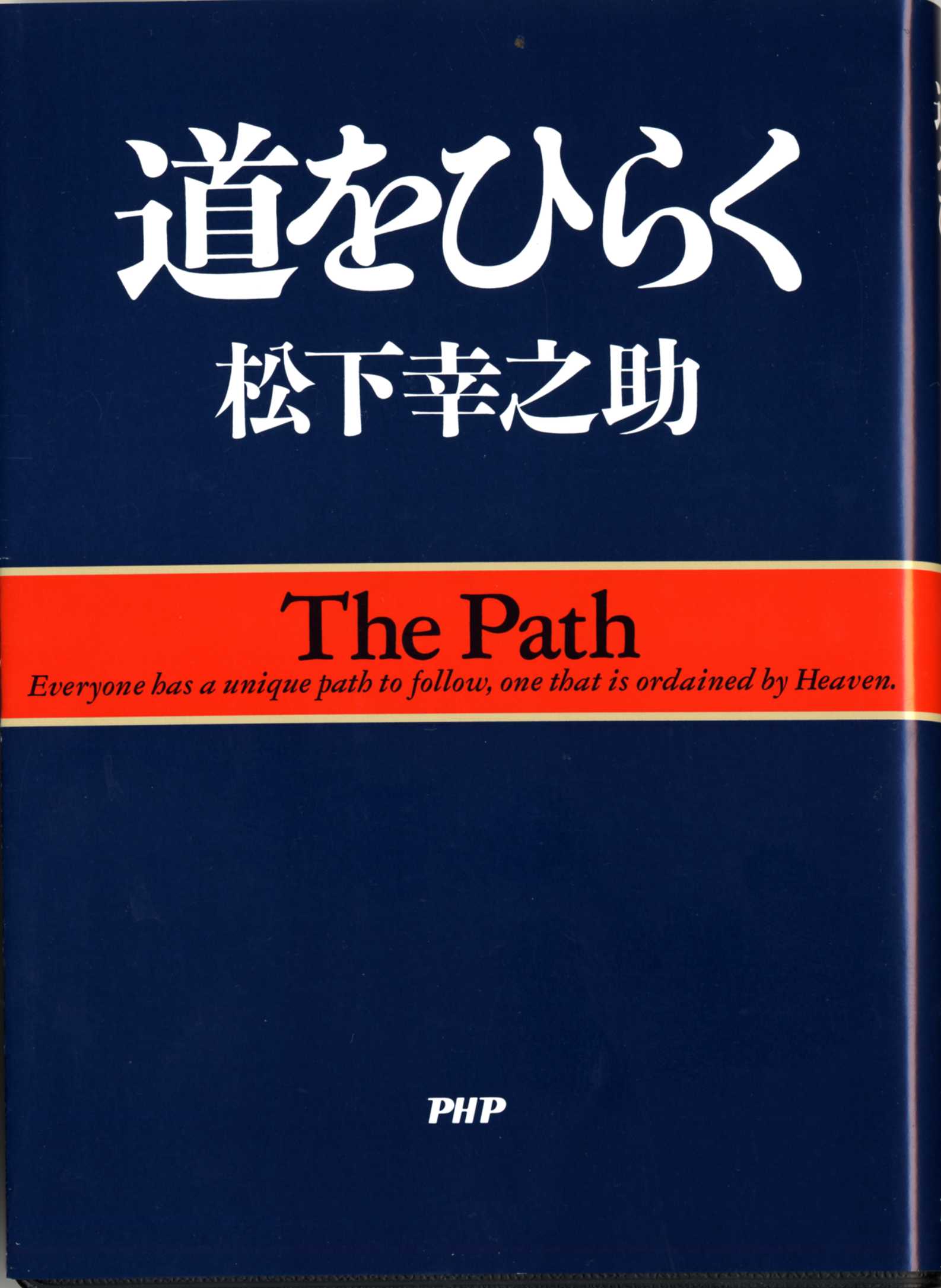弊社では,技術士第二次試験対策として“過去問の分析とその結果の活用”を重視しています。
JTAPCOブログでもこれまで何度も“過去問の分析とその結果の活用”について書きました。“しつこい”ぐらい書いています。
では,なぜ,“過去問の分析とその結果の活用”を重視するのか?
これには,2つの理由があります。
*理由1:友人が“過去問の分析とその活用”を行い,それが試験の合格の1つの要因になったこと
*理由2:技術士第二次試験の対策本を2冊執筆したこと 
■理由1について
理由1の内容は,2018年9月7日に掲載したブログで書きました(ブログのテーマ:技術士第二次試験対策:過去問を活用する「過去問を分析する」)(こちら)。
Hさんが行なっていた過去問の分析とその活用方法を見て「なるほど,こんな方法があったのか!」と思いました。
Hさんが受験したときには私は技術士の資格をすでに持っていたのでこの方法を採用にすることはなかったのですが,Hさんより後に受験していたら間違いなくこの方法を採用にしていたと思います。
Hさんの合格を見て,“過去問の分析とその結果を活用すること”は,試験に合格するための重要な対策の1つであることを認識しました。
■理由2について
弊社では,オーム社さんから建設部門を対象とした技術士第二次試験の対策本を2冊出版しています。
*「技術士第二次試験 建設部門 完全突破」(共著):こちら
*「技術士第二次試験 建設部門 答案作成のテクニック 5つの手順で書いてみよう」:こちら
これら2冊とも,建設部門のすべての選択科目(11の選択科目)の過去問の要約を載せています。
「技術士第二次試験 建設部門 完全突破」は平成21年度~平成25年度までの5年間の過去問を対象としており,「技術士第二次試験 建設部門 答案作成のテクニック 5つの手順で書いてみよう」は平成25年度~平成28年度までの4年間の過去問を対象としています。

過去問の要約の原稿を作成するため,平成21年度~平成28年度までの8年間のすべての選択科目(11の選択科目)の問題を読みました。
この作業を通して,以下のことがわかりました。
■各選択科目で出題傾向があること
■各選択科目での出題内容の範囲(どのような内容の問題が8年間で出ているのか)
平成21年度~平成28年度までの8年間のすべての問題を読むことによって得られたこれらの結果は受験勉強に活用できることもわかりました。
例えば,“選択と集中”による受験勉強ができることや予想問題を考えるときの参考になることです。選択と集中”による勉強ができれば受験勉強の時間を有効に使うことができます。
対策本の執筆に伴う過去問の分析から,“過去問の分析とその結果を活用すること”は受験勉強での重要な対策の1つであることがわかりました。
過去問の分析方法とその結果の活用方法に決まった方法はありません。
これらを独自に考えても結構注)ですし,弊社のセミナーに出席していただき弊社の方法を学んでいただいても結構です(こちら)。
注):できる限り長い期間を対象として過去問を分析してください。期間が長い方が過去問を有効に活用できます。
来年度の試験での合格を目指す方は,“過去問の分析とその結果を活用すること”を受験勉強の方法の1つと考えてこれを実践してください。