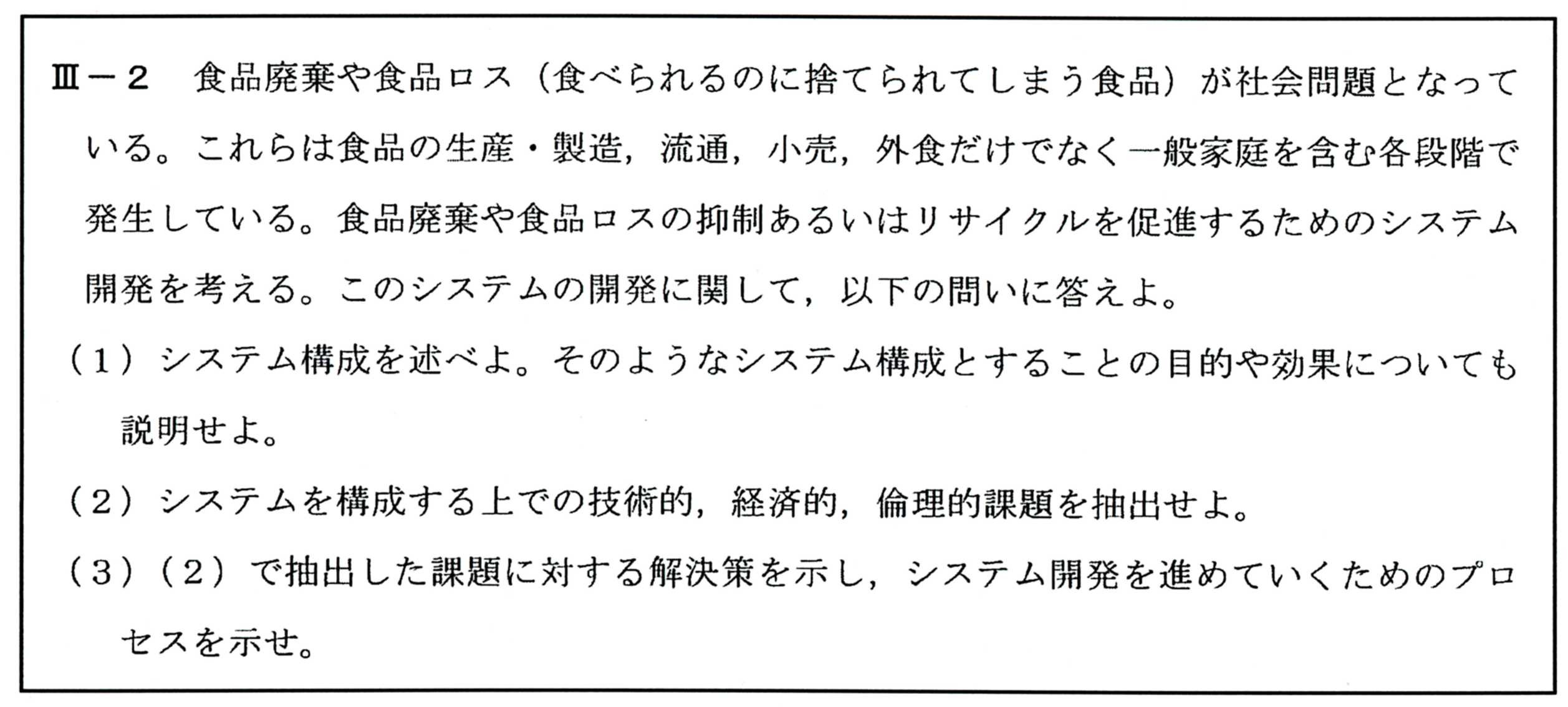“出社困難”という言葉を知っていますか?
「“帰宅困難者”という言葉は知っているが“出社困難”という言葉は知らない」という方が多いのではないでしょうか。
“帰宅困難者”という言葉の意味は,勤務先や外出先で地震などの自然災害に遭遇して自宅に帰るのが困難になった人のことです。
2011年3月11日に発生した東日本大震災で“帰宅困難者”という言葉が注目されました。
東日本大震災の発生で,首都圏の鉄道やバスなどの公共交通が運行停止になったため,首都圏に勤務する多くの方などが自宅に帰れませんでした。駅で一夜を過ごした人の映像をテレビで見た記憶があります。
“出社困難”という言葉の意味はこの逆です。“出社困難”という言葉の意味は,地震などの自然災害に遭遇して会社などの勤務先に出勤できないことです。
この“出社困難”という言葉は,今年(2018年)の6月18日に発生した“大阪府北部地震”で注目され,自然災害発生時の新たな課題としてクローズアップされました。
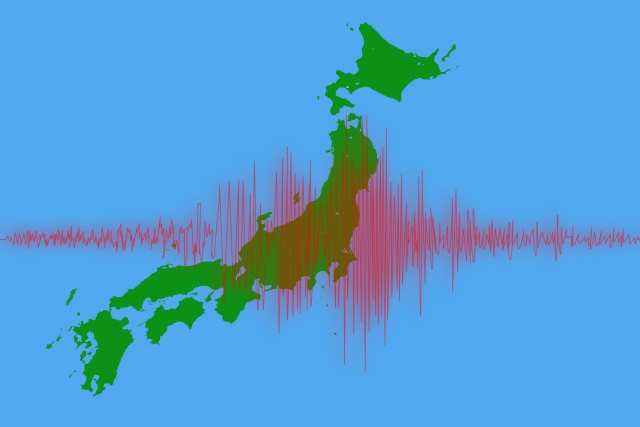
“大阪府北部地震”は,ちょうど出勤の時間帯の7時58分ごろに発生しました。この地震によって鉄道やバスなどの公共交通が運行停止になったため勤務先に行くことができない人が多く出ました。公共交通が運行停止になったため歩いて会社に行った方も多かったようです。
道路を歩く多くの会社員などを撮影した映像をテレビのニュースで見ました。
朝のNHK・ラジオのニュースで“出社困難”という言葉を知りました。
このような緊急事態のときには無理して勤務先(会社など)に行く必要はないと思いますが,会社を休んだら他の人から何か言われるかもしれないという心配があるようです。
ある大学の先生が以下のようなことをこのニュースの中で話していました。
歩いて出勤中に事故にあったらその人の処置が必要である。これにより本来助けなければならない人に救助の手が回らなくなるという問題がある。
この問題は“出社困難”の場合だけではなく“帰宅困難者”の場合にも当てはまりますが,確かに,この先生が指摘しているような問題はあると思います。
また,このニュースの中で,東京都で帰宅困難対策を担当する方の話もありました。
“出社”は企業の生産活動に係わることなので行政側から「○○してください」という指示はできない。企業側で,地震などの自然災害に遭遇して会社へ行くことが困難になった場合の対応方法を決めて欲しい。
このニュースの中で,鉄道やバスなどの公共交通が運行停止になったため会社まで歩いた女性の話を紹介していました。
この女性は,公共交通が運行停止になったため会社にそのことを電話で伝えたそうです。会社からそこ(たぶん駅)で待機するように指示があったのですがしばらく待っても連絡がないので会社まで歩いたそうです。
会社側もこのような緊急事態での対応のルールがなかったため混乱していたのだと思います。

2011年3月11日に発生した東日本大震災で“帰宅困難者”という言葉が注目され,2018年6月18日発生した大阪府北部地震で“出社困難”という言葉が注目されました。
「スーパーコンピューターによる解析能力が向上しても,AI(人工知能)が発達しても,地震などの自然災害が実際に発生することでわかることがある」ということです。