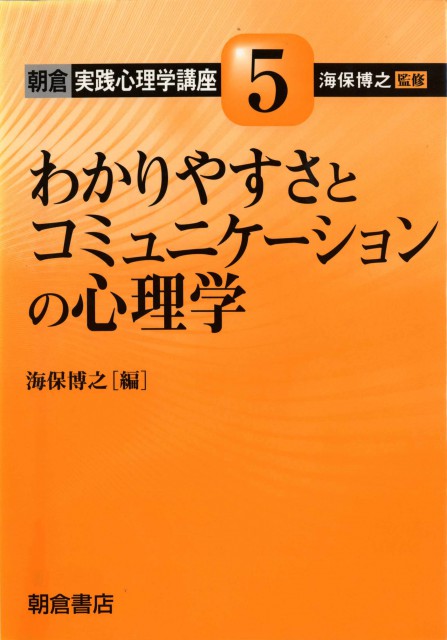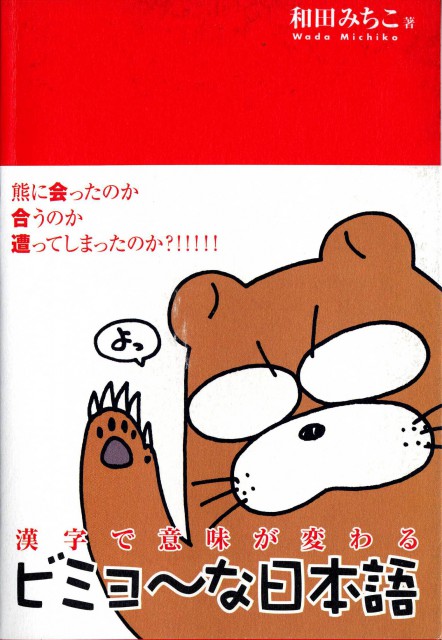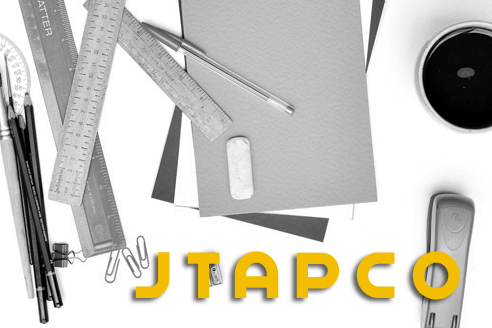今回は,「わかりやすさとコミュニケーションの心理学」を紹介します。
◆「わかりやすさとコミュニケーションの心理学:海保博之編:朝倉出版」
この本は,わかりやすさを心理学から解説しています。
わかりやすい文書を書くための考え方を突き詰めていくと,心理学,特に,認知心理学に当たります。
認知心理学とは,人間の学習や理解,記憶,思考,言語などを扱っている分野です。人間に入ってきた情報が,どのような過程で処理されるのかを扱う心理学とも言えます。
人間に入ってきた情報の処理過程をコンピュータに例えて解説している書籍もあります。
2016年8月6日(土)のブログで紹介した,「間違いだらけの学習論(西村克彦著)」も認知心理学をベースにした内容です(こちらを参照してください)。
今日のブログで紹介する本は,わかりやすさを認知心理学の視点から解説した内容です。
「第5章 文書コミュニケーションをわかりやすくする」の中に「5.図・表・イラストの利用」という項があります。
著者は,
「文書は,文章とグラフィックから構成されている。・・・(略)・・・。文章に加えて,図・表・イラスト(まとめてグラフィックとよぶ)をうまく利用することで文書は格段にわかりやすくなる」
と書いています。
著者は,別途,グラフィックとして,チャート(フローチャートなど)や写真も加えています。なお,絵はイラストの中に含めています。
著者は,グラフィックの3つの機能について解説しています。
*1番目 注意機能:これは読み手の注意をひくという機能である。
*2番目 記憶機能:文章だけでは記憶に残りにくいことでも,グラフィックを使ってイメージ化することによって記憶に残りやすくなる。
*3番目 説明機能:これは文章だけでは伝えにくい現象やデータを,見てわかるようにすることである。
弊社の「わかりやすい文書の書き方」の中の「6つのルールと17の書き方」にも,「ルール3(分けて書く) 書き方9:表で書く」と「ルール5(視覚的に書く) 書き方11:写真や図を入れて書く」があります。
著者が解説しているように,文書の中にグラフィックを入れると内容のわかりやすさが格段に向上します。その意味からもグラフィックの使い方は,「わかりやすい文書を書くうえでのポイント」と言うことができます。 ただし,特に,図や写真を入れるときの注意点がありますが・・・・。
「グラフィックの3つの機能」を頭に入れてグラフィックを活用してください。必ず,わかりやすい文書が書けます。