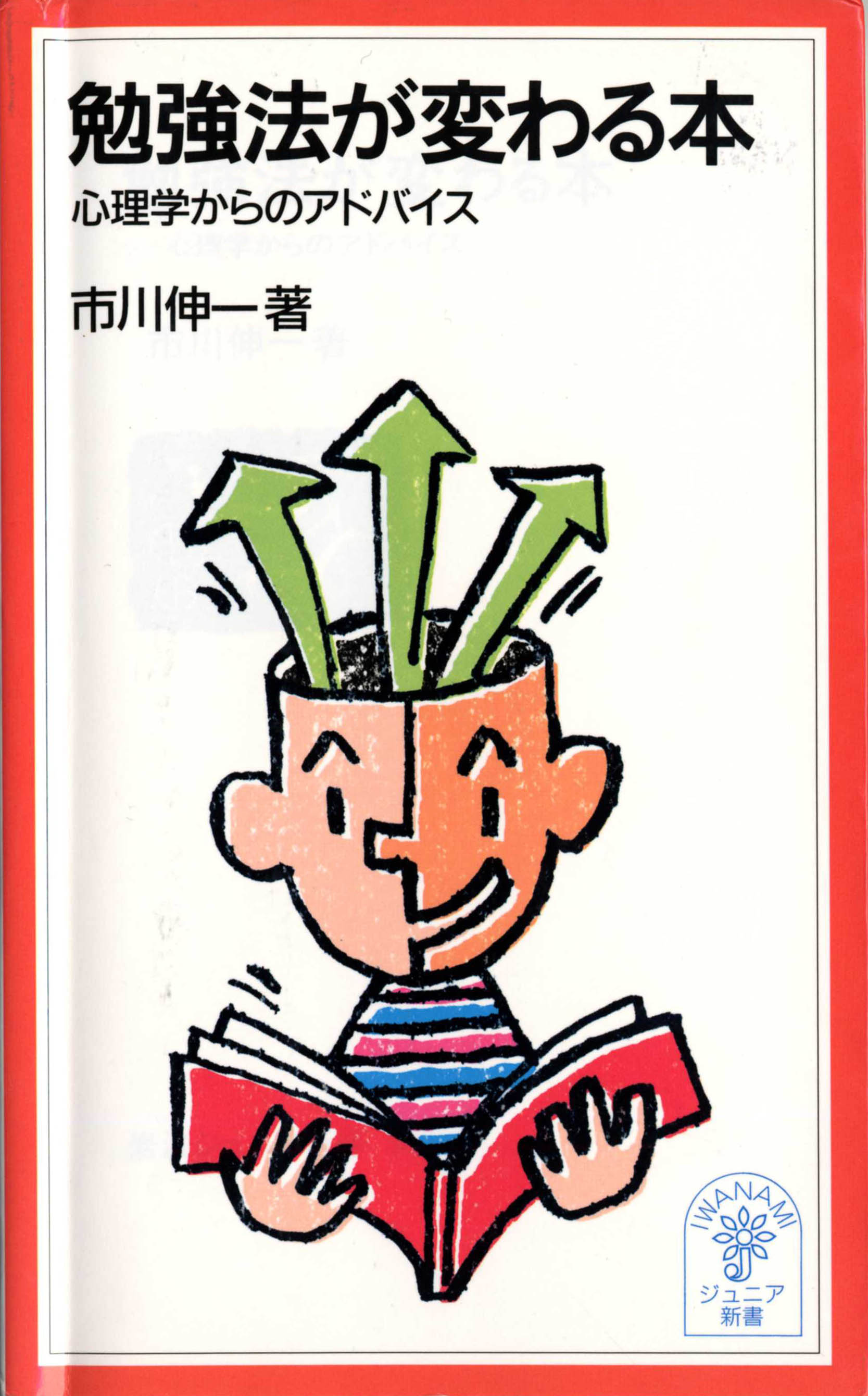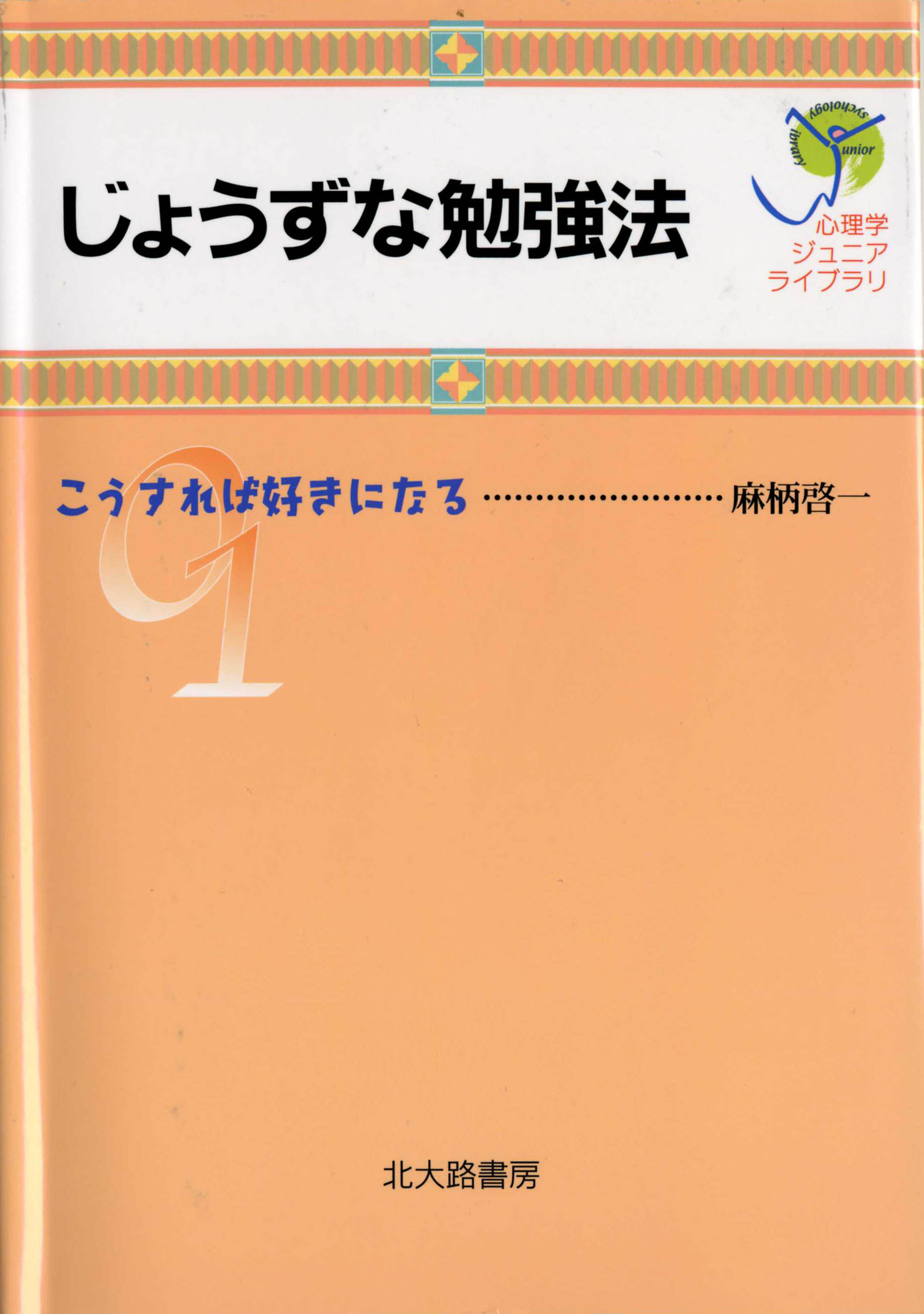今回は,「勉強法が変わる本」を紹介します。
◆「勉強法が変わる本:市川伸一著:岩波ジュニア新書(岩波書店)」
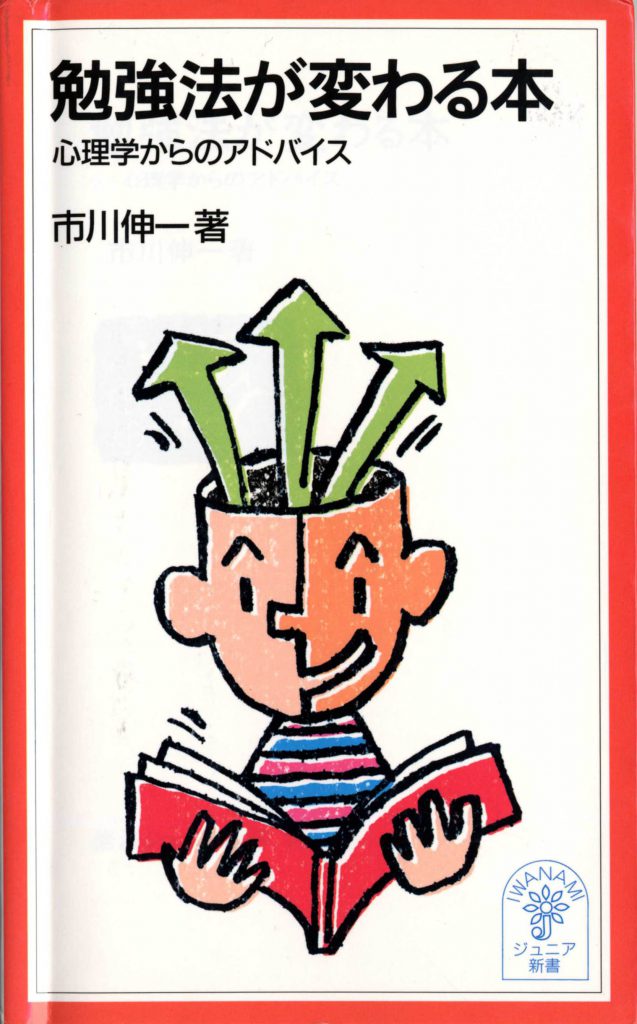
著者の市川氏は認知心理学者です。
これまでも,「これまでに読んだ本から」の中で認知心理学に関連した本を紹介しましたが,今回の「勉強法が変わる本」も認知心理学に基づく内容です。
この本は,中学生や高校生を対象にした内容です。認知心理学に基づく内容ですが中学生や高校生の勉強法をわかりやすく説明しています。「中学生や高校生のときにこの本を読んでいたら勉強法が変わっていただろう」と思うような内容です。
この本の中で著者は,認知心理学に基づく勉強法を解説しています。この勉強法は丸暗記による勉強法とは違います。「記憶する・理解する・問題を解く・文章を書く」という構成に基づき具体的な勉強法を解説しています。
ところで,以前,ブログの中で以下のことを書きました(こちら)。
認知心理学とは,人間の学習や理解,記憶,思考,言語などを扱っている分野です。人間に入ってきた情報が,どのような過程で処理されるのかを扱う心理学とも言えます。
「わかりやすい文書」とは「理解しやすい文書」と言い換えることができます。弊社でも以前,「わかりやすい文書の書き方」を「理解しやすい資料の作成方法」としていたこともあります。

認知心理学が,人間の理解や記憶などを扱う分野であることを考えると,認知心理学が,わかりやすい文書(理解しやすい文書)を書くうえで参考になることがわかります。
例えば,この本の「3.理解する」の中で,“先行オーガナイザー”という認知心理学の専門用語が出てきます。以下のブログも“先行オーガナイザー”に基づく内容です。
* 「わかりやすく説明する(先行オーガナイザーの考え方を使って説明する:パートⅠ)」:(こちら)
*「わかりやすく説明する(先行オーガナイザーの考え方を使って説明する:パートⅡ)」:(こちら)
「勉強法が変わる本」の中で印象に残っている文があります。「3.理解する」という章の中で書かれている文です。
自分がわかっているのか,いないのか,どうももやもやしているというときに,説明できるかどうかでチェックしてみるというのはすごく大切な勉強法だ。
説明すべきことを掘り下げて理解していることで説明できます。
伝えるべき内容を書き手が掘り下げて理解していることでわかりやすい文書が書けます。
「説明するとき」も「わかりやすい文書を書くとき」も,「掘り下げて理解する」が重要なキーワードです。